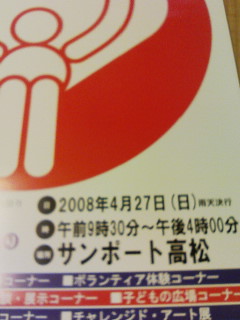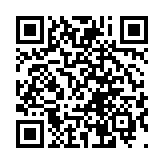2008年04月28日
『障害児殺しの思想』 横田弘著(JCA出版 1979年発行)
先週(2008年4月)、テレビのニュースが伝えた・・・
「発達が遅れている」ことを苦にして、母親が幼い子を殺し、自分も手首を切り、自殺未遂となったと・・・
なぜに、日本は悲しい物語が繰り返される国なのか
《障害児は何故殺されなければならないのか》
また、一人、障害児が殺された。
歩けないということだけで、
手が動かないというだけで、
たったそれだけの理由で、
「福祉体制」のなかで。
地域のひとびとの氷矢のような視線のなかで、
その子は殺されて行った。
1978年2月9日、
何気なく見ていた午後11時のテレビニュースが、
さりげない口調でこの事件を伝えたとき、
ストーブが暖かく燃える部屋にいながら、
私は一瞬のうちに自分の内側が凍りついた夜の荒野に
彷徨い出ていくのをしっかりと捉えていた。
「殺された障害児」が私と同じ横浜、
しかも、日本脳性マヒ者協会「青い芝」神奈川連合会の事務局が存在する、
港北区内に住んでいたということもあるかもしれない。
今年になってから朝日新聞で報じられただけで、
もう、3,4件の障害児が殺される
ということが重なっているせいかもしれない。
しかし、そうしたこととは別に、私は今度の事件の底に、
言い知れぬ私自身の黒い未来を見い出した想いだったのだ。
何故、障害児は殺されなければならないのだろう。
なぜ、障害児は人里はなれた施設で生涯を送らなければならないのだろう。
何故、障害児は街で生きてはいけないのだろう。
ナゼ、私が生きてはいけないのだろう。
社会の人々は障害児者の存在がそれ程邪魔なのだろうか。
私の胸には、三、四日前に、
事務所に配達された一通のはがきの言葉がフッと蘇ってきた。
人間としての権利を奪われたとは何事だ!
お前達片端者は世の中を遠慮して
ソット生きていけ!
それでこそ始めて我々五体健全な人達から
同情を得られるぐらいの事はいくら脳性馬鹿でも解ると思う
親の因果が子に報い!
因果律という言葉を知らないか?!
逆上せ上るのも程々にしろ!
片端者奴
(一市民より)
1979年1月に発行された『障害児殺しの思想』は、このような書き出しで始まっている。
「発達が遅れている」ことを苦にして、母親が幼い子を殺し、自分も手首を切り、自殺未遂となったと・・・
なぜに、日本は悲しい物語が繰り返される国なのか
《障害児は何故殺されなければならないのか》
また、一人、障害児が殺された。
歩けないということだけで、
手が動かないというだけで、
たったそれだけの理由で、
「福祉体制」のなかで。
地域のひとびとの氷矢のような視線のなかで、
その子は殺されて行った。
1978年2月9日、
何気なく見ていた午後11時のテレビニュースが、
さりげない口調でこの事件を伝えたとき、
ストーブが暖かく燃える部屋にいながら、
私は一瞬のうちに自分の内側が凍りついた夜の荒野に
彷徨い出ていくのをしっかりと捉えていた。
「殺された障害児」が私と同じ横浜、
しかも、日本脳性マヒ者協会「青い芝」神奈川連合会の事務局が存在する、
港北区内に住んでいたということもあるかもしれない。
今年になってから朝日新聞で報じられただけで、
もう、3,4件の障害児が殺される
ということが重なっているせいかもしれない。
しかし、そうしたこととは別に、私は今度の事件の底に、
言い知れぬ私自身の黒い未来を見い出した想いだったのだ。
何故、障害児は殺されなければならないのだろう。
なぜ、障害児は人里はなれた施設で生涯を送らなければならないのだろう。
何故、障害児は街で生きてはいけないのだろう。
ナゼ、私が生きてはいけないのだろう。
社会の人々は障害児者の存在がそれ程邪魔なのだろうか。
私の胸には、三、四日前に、
事務所に配達された一通のはがきの言葉がフッと蘇ってきた。
人間としての権利を奪われたとは何事だ!
お前達片端者は世の中を遠慮して
ソット生きていけ!
それでこそ始めて我々五体健全な人達から
同情を得られるぐらいの事はいくら脳性馬鹿でも解ると思う
親の因果が子に報い!
因果律という言葉を知らないか?!
逆上せ上るのも程々にしろ!
片端者奴
(一市民より)
1979年1月に発行された『障害児殺しの思想』は、このような書き出しで始まっている。
2008年04月27日
2008年04月24日
本日、4月例会のご案内
4月24日(木)午前10時半~午後2時(都合の良い時間にお越しください。)
場 所 高松市男女共働参画センター (2F) 高松市錦町高松工芸高校の北東側
場 所 高松市男女共働参画センター (2F) 高松市錦町高松工芸高校の北東側
2008年04月20日
広報活動始めてます!


4月18日(金)、朝、今年度受検の「特別措置」における不適切な対応について、関係者に報告させていただきました。
また、午後はノーベル文学賞のメダル(本物デス、ステキだった
 )を拝見後、(国宝の掛け軸も拝見いたしました。ふーむ、江戸時代の作品これも凄かった!)ここに招待してくださったキシャさんにも報告させていただきました。(彼女と私は、あまりに可愛そうな話にお互いに涙を流しながらの取材風景でした。。。)
)を拝見後、(国宝の掛け軸も拝見いたしました。ふーむ、江戸時代の作品これも凄かった!)ここに招待してくださったキシャさんにも報告させていただきました。(彼女と私は、あまりに可愛そうな話にお互いに涙を流しながらの取材風景でした。。。)みんな、特にカンケイシャは真実(現実)を知らなければなりません。
私事ですが、我が子の今年度にいたる4年間の公立高校受験(公立の中高一貫校も小学6年生のときに受検経験あるので合計8回、毎年1次は全日制を受検、そして、不合格なので2次募集の定時制を受検、2年目は姉の大学の卒業式があったので、定時制は受検しませんでした。)で香川県が行っている障害がある生徒への「特別措置」について、ただ今「温故知新中」デス。
2008年04月19日
イタシカタノナイコト!?
定員内不合格についての見解を伺いました。
私たちは「アッテハナラナイコト!!」と思っています。
たくさんの子どもたちの、親たちの悲しみを知っているから。。。
*詳しくは「らび」参照
私たちは「アッテハナラナイコト!!」と思っています。
たくさんの子どもたちの、親たちの悲しみを知っているから。。。

*詳しくは「らび」参照
2008年04月15日
『障害児と共に学ぶ』アリソン・ヴァーハイマー著

紫雲山頂の桜並木から見た瀬戸内海
とっても、美しかった

《人権問題としてのインクルージョン》
★障害者は普通の制度や地域社会から排除されるべきではないし、
その障害を理由に分離されるべきでもない。
これは基本的人権の問題なのである。
これまで障害をもっている子どもと大人に対する分離が続いてきた。
しかし、人権や性の違いを根拠にした強制的な分離をもはや許容するこのない社会では、
こうした分離は全く受け入れられるものではない。
分離はすべての人々に影響をあたえるものであり、
だからこそ、すべての人間の問題として
理解されなければならないのである。
★障害を持っていない子どもたちは、
障害を持った子どもたちから分離されることで
ハンディキャップを与えられているのである。
したがって、われわれすべてが、
分離がもたらす偏見の結果に悩んでいるのである。
★人権侵害であるのに、
心地よい言葉でそれを隠してしまうという、
憂うつにさせられる傾向が見られる。
「強制的な分離」の現実を認めるよりも
「特別」教育について語るほうが容易なのである。
われわれはすべて「特別」と感じるにのを好むのである。
「特別」という言葉は私たちの気分を良くするが、
障害児の家族が証言するように、
いわゆる「特別教育」は排除されることの痛みと深く関わっている。
障害を持つ人々と持たない人々との
日常的な関係が否定されるということは、
不健全なことであり、受け入れがたいものである。
インクルージョンというのは、
違いを理由にして分離されてはならないという
基本的人権の問題である。
その認識を誤ると、
人権認識に欠ける慈善や善意の行為として、
非障害者が障害を持っている人々を
「自分たちの世界」に招き入れてあげる、
という状況が生み出されてしまうのである。
明石書店 700円
2008年04月10日
普通学級の障害児の通知表が語るもの
ーワニなつ・いろはカルタのノートー(佐藤陽一ブログより)
《こ》
子どもの通知表、ついているのは先生の点。
普通学級の障害児の通知表は、だいたいがオール1かオール△か、
とにかくビリの評価がつく。
さんすうも、おんがくも、たいいくも、
障害のない子たちと比べたら、やっぱりそうなるのかもしれない。
でも、時々、音楽の選科の先生が2をつけてくれたりすることがある。
選科の体育の先生が2をつけてくれたりすることがある。
また、先生が変わると、評価が変わることがある。
たとえば、ずーと字を書かない子、しゃべらない子は、
その子の「学力」が変わった訳ではないのだから、
その「変わった評価」の差は何か。
それは、障害を持った子どもたちの側からみた「先生の点」だったりするのだろう。
(この子たちは人間を数字や△の記号なんかで評価するほど野蛮じゃないと思うけど。)
でも、一番下の1や△をつけるのも、
「教師のプライドが許さない」という先生がいて、
そういう人たちは、誰が教えた訳じゃないだろうに、
不思議と同じことをする。それが「斜線」だ。
そして、その理屈もたいがい同じだ。
「1をつけたら、他の子の1がかわいそう」
「△をつけたら、他の△の子がかわいそう」
そんな悲しい理屈を思いつく人生がかわいそうだと、私は思う。
親が斜線の通知表にちゃんと抗議して、
他の子と同じ通知表を下さい、というと、
「そんなに言うなら、1をつけますが、
普通の1じゃなくて、ずっと低い1ですからね」と、
訳の分からないことをいう人もいる。
そんなくだらない理屈が「自分の評価」だと知っておいた方がいい。
「うちの子、全部1だけど、社会だけ2だったの」という話を聞いて
私たちは応える。
「そうか、社会の先生だけが、ちょっとましなんだね」
「え、そうなの?うちの子が社会がんばったんじゃないの?」
「でも、しゃべらないのも、字を書かないのも、 テストが0点なのも変わらないでしょう」
「そうね~」
「子どもが変わったわけじゃないんだから、
通知表の評価は、先生の評価なんだよ。
この子はもともとがんばっているんだから、
社会のせんせいだけ、やっとこの子のがんばっている姿が見えるようになったんだね」
障害のある子どもたちの、小学校から高校までの通知表の話を毎年聞いていると、
分かることがある。
それは、言葉のない子や、字を書かない子でも、
高校の通知表がいちばん良くて、次が小学校で、一番悪い成績が中学校だ。
誰か、このテーマで論文でも書いて発表したら面白いのに。
《こ》
子どもの通知表、ついているのは先生の点。
普通学級の障害児の通知表は、だいたいがオール1かオール△か、
とにかくビリの評価がつく。
さんすうも、おんがくも、たいいくも、
障害のない子たちと比べたら、やっぱりそうなるのかもしれない。
でも、時々、音楽の選科の先生が2をつけてくれたりすることがある。
選科の体育の先生が2をつけてくれたりすることがある。
また、先生が変わると、評価が変わることがある。
たとえば、ずーと字を書かない子、しゃべらない子は、
その子の「学力」が変わった訳ではないのだから、
その「変わった評価」の差は何か。
それは、障害を持った子どもたちの側からみた「先生の点」だったりするのだろう。
(この子たちは人間を数字や△の記号なんかで評価するほど野蛮じゃないと思うけど。)
でも、一番下の1や△をつけるのも、
「教師のプライドが許さない」という先生がいて、
そういう人たちは、誰が教えた訳じゃないだろうに、
不思議と同じことをする。それが「斜線」だ。
そして、その理屈もたいがい同じだ。
「1をつけたら、他の子の1がかわいそう」
「△をつけたら、他の△の子がかわいそう」
そんな悲しい理屈を思いつく人生がかわいそうだと、私は思う。
親が斜線の通知表にちゃんと抗議して、
他の子と同じ通知表を下さい、というと、
「そんなに言うなら、1をつけますが、
普通の1じゃなくて、ずっと低い1ですからね」と、
訳の分からないことをいう人もいる。
そんなくだらない理屈が「自分の評価」だと知っておいた方がいい。
「うちの子、全部1だけど、社会だけ2だったの」という話を聞いて
私たちは応える。
「そうか、社会の先生だけが、ちょっとましなんだね」
「え、そうなの?うちの子が社会がんばったんじゃないの?」
「でも、しゃべらないのも、字を書かないのも、 テストが0点なのも変わらないでしょう」
「そうね~」
「子どもが変わったわけじゃないんだから、
通知表の評価は、先生の評価なんだよ。
この子はもともとがんばっているんだから、
社会のせんせいだけ、やっとこの子のがんばっている姿が見えるようになったんだね」
障害のある子どもたちの、小学校から高校までの通知表の話を毎年聞いていると、
分かることがある。
それは、言葉のない子や、字を書かない子でも、
高校の通知表がいちばん良くて、次が小学校で、一番悪い成績が中学校だ。
誰か、このテーマで論文でも書いて発表したら面白いのに。
2008年04月04日
進化する特別支援教育(→真のインクルージョンへ)

二次募集不合格発表の朝、曇り空だったのに、なぜか我が家のリビングから日の出をみた

(ホンマニ、ポジティブだわ
 )
)『キング牧師の力づよいことば』より
<変換形・・・さぬきバージョン
「わたしには 夢が あるのです。
あの香川県においてさえ いつの日か きっと、
多くの高校の生徒たちや教師たちが
知的障害のある生徒と、
仲間として、恩師として 手をとりあい、
力を合わせる日が くるだろうと」
 4月2日の新聞報道によれば、
4月2日の新聞報道によれば、新しい県教育長細松氏(前県健康福祉部長)が就任会見(1日)で
「初めて教育行政に携わるが、これまでの経験を生かしてとりくみたい」と抱負を述べた。
重要課題として、県立高校の再編整備とスポーツ、伝統文化の振興を挙げた。
”現場で使命感を持って頑張っている教師が生き生きと働けるよう、力を結集したい” (毎日新聞より)
2008年04月03日
キング牧師(アメリカ公民権運動の父)

今朝、NHKテレビ『おはよう日本』でキング牧師が亡くなって40年が経つという。40年前の4月4日、テネシー州メンフィスで彼は暗殺された。
テレビの映像は、キング牧師が夢を語っている姿を映し出す。
彼は人々に夢を語る
「私たちの子どもたちが肌の色で差別されず、人格で評価される日がくることを夢みる!」と・・・・
私も夢みる
「障害のある子どもたちが能力により差別されず、人格で評価される日がくることを!」
2008年04月02日
実態調査開始
1、 が受検した20年度公立高校の合否にかかるすべての書類
が受検した20年度公立高校の合否にかかるすべての書類
特別措置願書(様式11)の作成
障害のある志願者について、受検上の特別な配慮が必要な場合に、・・・・・
積極的な差別是正措置であるアファーマチィブ・アクションをいかにして創りだしていくか。
まずは今までの実績を調査しましょう。
2、20年度公立高校選抜における定員内不合格者の数
教育行政が適性に行われているか調査するため
教育委員会の担当者は昨年と同じSさんでした。県の職員は沢山移動になっていました。
過去の蓄積とともに、しっかりと調査させていただきます
 が受検した20年度公立高校の合否にかかるすべての書類
が受検した20年度公立高校の合否にかかるすべての書類特別措置願書(様式11)の作成
障害のある志願者について、受検上の特別な配慮が必要な場合に、・・・・・
積極的な差別是正措置であるアファーマチィブ・アクションをいかにして創りだしていくか。
まずは今までの実績を調査しましょう。
2、20年度公立高校選抜における定員内不合格者の数
教育行政が適性に行われているか調査するため
教育委員会の担当者は昨年と同じSさんでした。県の職員は沢山移動になっていました。
過去の蓄積とともに、しっかりと調査させていただきます

2008年04月02日
2008年04月01日
2008年3月31日 「サクラチル」便り&「ある決意」

第二章 「机上の空論」から「実践への道」
~ユニバーサルデザインの高校を求めて~
再び「教育の荒廃」と言う言葉の真意
できない子がいてこその営為
<石川先生は語る>
中学校や高等学校では教科担任制がとられ、それぞれ専門の免許証を持った教員が、その教科を指導するという形式をとっている。教えるべき学問内容が高度化してくるから、小学校のように、ひとりの教員がすべての教科を教えるというわけにはいかないのである。
・・・・・・中略・・・・・
ところで、教科教育ということであるが、これはその教科を教える、ということではない。教科を教える、のであったなら、音楽科とか美術科の授業が、義務教育の小・中学校に置かれるのはおかしい。音楽を教えて、音楽家としての素養を、日本中の子どもたちに身につけさせることなど、必要ないはずだからである。
音楽を通じて、豊かな人間的情操を育てようというのが、音楽科教育の目的であるはずだから、音楽を教えるのではなく、音楽で教えるのでなければならない。つまり、教科を教えるのであってはならず教科で教えるのでなければならないのである。
低い次元で低迷している子どもの意識や行動などを、教科教育や教科外教育で、より高次の意識や行動に高めてやろうというのが、現代の学校教育でとられている方法なのである。
この論理に照らしてみると、現在の学校現場には、おかしなことが多い。
「言うことをきかない子」が多い、「学級を乱す子」が多い、「教師に反抗する子」が多い、そして、「授業について来れない子」が多い、というふうな悩みが、どの学校にも大なり小なり存在する。これを学校の外からみると、「教育が荒廃している」ということなるのであろうか。しかし、これらの悩みは、前述の論理からすると、理屈に合わないことになるはずである。
低次元にいる子どもの意識を、より高次元の意識に高めるのが、「教科で教える」ことであるならば、国語科で、社会科で、音楽科で、その他すべての教科、教科外の指導で、「言うことをきく子」にさせ、「学級に協力する子」にさせ「授業について来れる子」にさせることこそが、教育そのものであるはずだからである。言い過ぎになることを恐れずに言えば、前の事情のワクの中でだけ考えれば、「言うことをきかない」「学校を乱す」「授業について来ない」実態があってこそはじめて教育が成立するのであって、これらの悩みがないところで行われるものは、それは教育ではない、ということになりはしないか。「言うことをきかない子」「学級を乱す子」「授業について来れない子」を、国語科でどう変えるか、数学科でどう変えるか、音楽科でどう変えるか、などということが、教科担任教師としての力量をはかるインデックス(指標)である、とすら言えるのではないだろうか。
そういうことが、できない(と言うより、やろうとしない)教師、あるいは原理的にも方法的にもなにも対応策を考えようとしないで、ただやたらに叱るだけの教師、などなど、そういう学校現場でしかないからこそ、「教育が荒廃している」ということになるのではないだろうか。
世間で言われている「教育の荒廃」ということばの意味は、教師非難のニュアンスを強く持つものなのである。教師たちよ、甘えてはいけない。 (中学校教諭)